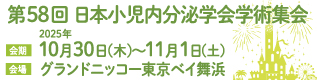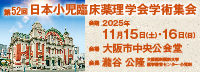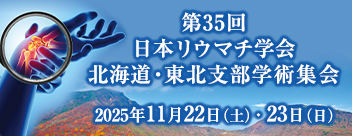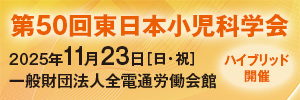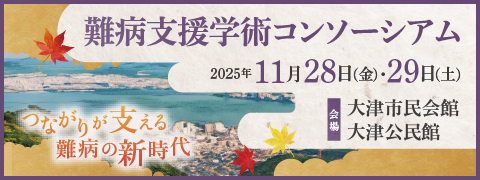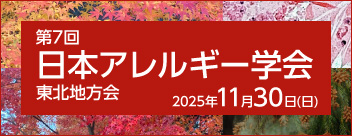会長挨拶

第35回日本小児リウマチ学会総会・学術集会
会長 岡本 奈美
労働者健康安全機構大阪ろうさい病院 小児科/
大阪医科薬科大学 小児科
第35回日本小児リウマチ学会総会・学術集会を2026年10月16日(金)~18日(日)の3日間にわたり、大阪市中央公会堂(大阪市北区中之島)において開催させていただきます。 本学会は1991年に日本小児リウマチ研究会としてはじまり、2001年の第13回から日本小児科学会分科会として日本小児リウマチ学会に改名となりました。その後も国内のリウマチ医・国外の小児リウマチ医との連携を深めつつ、着実に発展してきた本学会の学術集会を開催させていただけること、幸甚の至りであります。
本学会が対象とする小児リウマチ性疾患(類縁疾患を含む)の多くは希少疾患で、かつて医療現場にあっても認知度が低く、診断や治療まで時間を要していました。現在、小児リウマチ専門医の増加(20年間で約4倍!)、医療技術の進歩や情報ネットワークの革新、ガイドラインによる標準的治療の普及により各段に予後が改善してきております。これは本学会や、関連する研究班が教育・研究・啓発に大きく貢献してきた成果と考えます。国際的にも、毎年原因遺伝子や病態、それから治療につながる新たな知見が報告されており、疾患領域を横断するような新たな免疫制御療法の臨床応用が広がりつつあります。また、子どもの生命・機能予後改善は、移行期医療という概念の普及にもつながり、AYA世代患者に対する支援や成人診療科との連携など、今後ますます本学会の果たすべき役割は非常に大きいと考えます。
華やかな未来を夢見ると、つい過去の事は箪笥の引き出しにしまわれがちですが、私自身が若年性特発性関節炎の手引きやガイドライン作りに携わる際に感じたことは、過去の資料から経緯を知り頭の中を整理する事、何が必要で何が足りていないか(いわゆるニーズとシーズ)を把握する事の重要性です。また、検査手段の乏しい時代の医師は今よりも注意深く患者の外なる声と内なる声に耳を傾けており、医師としてのスピリットに触れるきっかけにもなりました。いつの時代も、小児リウマチ医はどうすれば患児の成長や人生がより豊かになるかを考え続けてきました。今回のテーマは、これまでの先人の果たしたこれまでの流れを理解し、未来の発展へつなげる意味合いを込めて、「Bridging old and new~Don’t be satisfied with the status quo~」といたしました。
ご参加いただいた方が、Dreams Come True寛解(武井修治先生命名)に向って患児・家族と共に歩んで頂ける一助となれば幸いです。
![Poster [PDF] Download ↓](./images/poster.jpg)